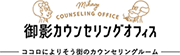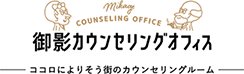4,文鳥さん「認知行動療法について」

「こんにちは~文鳥です。今日も勉強しにきました!」
「文鳥さん~!お待ちしておりました。お部屋へどうぞ~!」
「やぁやぁ、最近寒くなったような気もするが…調子はどうかのう。」
「こんにちは先生。最近、飼い主がおいしいおやつを買ってきてくれるようになって、とっても元気なんです!」
「今日は、ちょっと詳しいことを聞きたくて来ました。認知行動療法のことで…」
「ほう!!!」
「認知行動療法について詳しく知りたいとは、ずいぶん勉強をすすめたのじゃな~!関心関心。ウサギ助手、資料あるかのう」
「少し前に先生が作った資料ありますよ!すぐ持ってきます~」
「いつもありがとうございます!」
数分後・・・
「おまたせしました~なかなか見つからなくて。こちらです!」
「これじゃこれじゃ、ありがとう。」
「さて、認知行動療法は『行動療法』と『認知療法』というものを組み合わせた方法でのう。認知行動療法に入る前にこの2つからまずは説明するぞい。」
①行動療法について
・1958年にアイゼンクが提唱した方法である。
・さまざまな行動のもとには学習があると考え、学習の訓練により不適応行動を消去し,より好ましい行動を新た再学習することが目的である。
例:犬が怖い→不安階層表の作成
・・・犬に関する不安なことや怖いことを点数化する(0点:犬のキャラクターの絵をみる、10点:犬の写真をみる ~ 90点:犬カフェに行く、100点:犬を触ってなでる)。低いものから並べ、少しずつチャレンジする。
②認知療法について
・ベックが行動療法の考え方と、スキーマや自動思考、認知のゆがみの関係に基づいて提唱した、短期間で行う問題解決型の方法である。
・人間はいつも自分の状況を主観的に判断し、その判断がこころの状態に影響するとし、主観の中で歪んだ認知に働きかけ、こころの状態を変化させることを目的とする。
スキーマ:過去の経験や記憶によってつくられた考え方のクセのこと。
自動思考:自然に浮かんでくる考えのこと。同じ出来事に対しても、個人差がある。
認知のゆがみ:誤った思考のこと。0か100か思考や、過剰なマイナス思考、~すべき思考など。
「う~ん、私このあたり難しくて苦手です……。」
「ほっほっほ~、この2つが認知行動療法に繋がっているからよく覚えておくのじゃ。」
「文鳥さんはどうかのう。次に認知行動療法について説明してもいいかのう。」
「なんとなくですが、つかめてますよ!次もお願いします!」
(す、すごい…)
①認知行動療法とは
・心理療法の1つで、CBT(Cognitive Behavioral Therapy)とも呼ばれ、行動療法と認知療法を組み合わせた方法である。
・感情、身体、認知、行動がお互いに作用していると考え、変容することのできる認知と行動の部分にアプローチしていく。
・過去の研究結果に基づく考え方(エビデンスドベースド)から、有効である介入方法を導き出し行うという特徴がある。
・うつ病や不安障害、強迫性障害などの疾患に対しても効果的であることが明らかになっている。
・最近では「マインドフルネス」や「今ここ」の考え方や方法が積極的に用いられている。
「ふむふむ、行動療法と認知療法を合わせた方法で、エビデンスベースドが強みなんですね。」
「マインドフルネス、聞いたことはあるんですけど…どのような方法なんですか?それ以外の方法についても詳しく知りたいです。」
「マインドフルネスは、禅などの東洋文化を取り入れたものじゃ。最近知っている人も増えてきたように感じるのう。」
「よし。ウサギ助手、数日前にまとめてくれておったな、資料を頼む。」
「了解です!」
④さまざまな認知行動療法
・マインドフルネス
→意図的に「今、この瞬間」に、価値判断することなく注意を向ける方法である。禅や瞑想などの東洋の文化を取り入れており、集中力の向上やストレス軽減といった効果があるとされている。
・コラム法
→ある状況に対する気持ちや考えを書き出し、その考えの矛盾点に気付いたり、他の考え方を見つけることで、自分自身の自動思考やスキーマに気付く方法である。自己観察を続けることで、否定的な考えを持ちやすい自分に気付いたり、モヤモヤとしていた気持ちを整理することに役立つ。
・SST(social skill training)
→社会生活技能訓練とも呼ばれ、他者とうまく関わっていくために必要な対人行動を身につけるための方法である。ある場面を設定し、実際に演じながら(ロールプレイ)、良かった点や改善点を見つけ、試行錯誤を繰り返すことで、その場面に合わせた振る舞いや言葉遣い、自己主張の仕方などを身につけることができる。
「やはりエビデンスベースドであることから、認知行動療法は医療機関で扱われていることも多いのじゃ。」
「しかしながら心理療法はこころを相手にするから、一瞬で解決する、すぐ慣れるというわけではないのじゃ。マインドフルネスの練習や宿題など、繰り返し行うことが必要なものもある。少しずつ、少しずつ取り組むのじゃ。」
「だから、心理士と一緒に継続できる方法を考えながら取り組んでいくことが大切なのじゃ!」
「私、以前にSSTの勉強会に参加したことがあるんです。いつか私もプチ相談所でクライエントさんと取り組んでみたいです!」
「それもそうじゃのう。ウサギ助手にもっと活躍してもらえるといいのう。」
「はい、もっともっと勉強します~!」
「ふふふ、楽しみですね!」
「いやぁ~今日もわかりやすく学ぶことができました!いつもありがとうございます、カメ先生、ウサギ助手!」
「マインドフルネスも興味深いです。私もウサギ助手のようにもっともっと勉強しなくちゃですね!」
「勉強熱心なのは良いことじゃが、無理は禁物じゃぞ~。文鳥さんのペースで進めて、休む時は休むんじゃぞい!」
「はい。そうします!」
「あ、もうこんな時間!今日もあっという間でした~それでは失礼いたします。」
文鳥さんは急いで飛んで行ったのであった・・・・・・
「文鳥さん、すごいペースで勉強が進んでますね!ちょっと焦っちゃいました…。」
「そうじゃのう、ウサギ助手はウサギ助手のペースで、文鳥さんは文鳥さんのペースで良いのだが・・・最近の文鳥さんは頑張りすぎていないかちょっと心配じゃのう。」
「そうですね、あとからドッと来てないといいんですが…。」
「私も無理をしないこと、意識してぼちぼちでいきます!」
「うむ!そうしておくれ~」